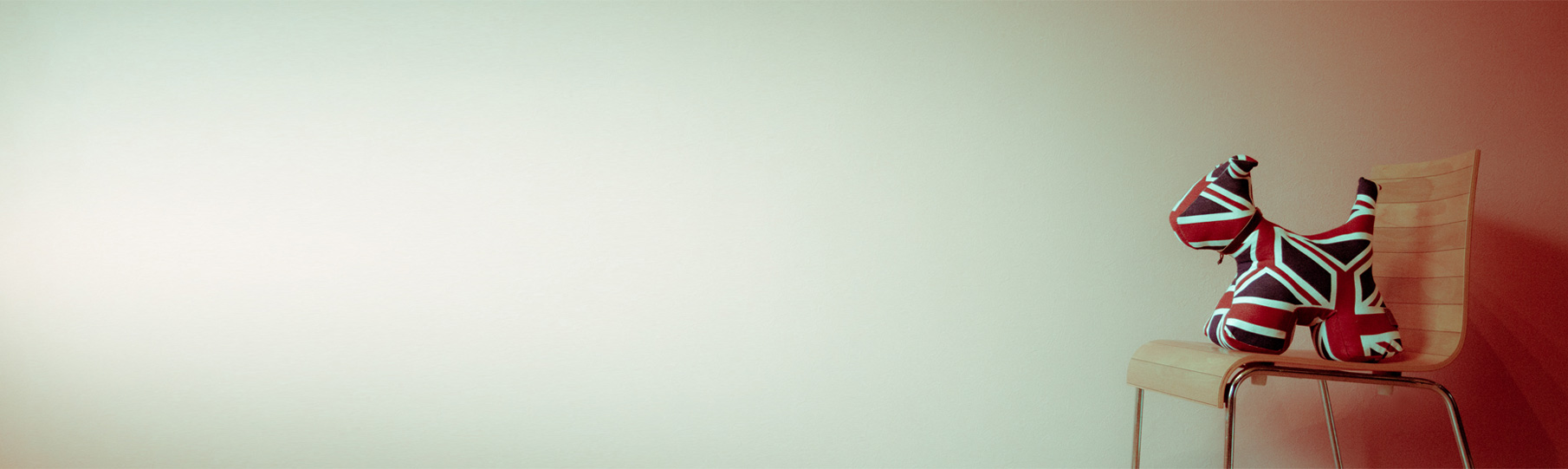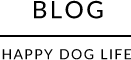失敗しない開業
2018/03/19 in DOG DIAMOND
『企業生存率』って誰もが一度は聞いた事があると思います
1年後で60%
10年後に5% とかのヤツですね・・・・
企業する人にとっては、こんな怖い話はないと思いますが現実です
もちろん、業種によって時代によって稼げる業種なのか条件は違います
でも普通に考えて、低賃金と言われているトリミング業界が稼げる業種の訳ないですよね
この先犬の数は右肩下がりに減っていくのは確実なのに、先を見越せる業種じゃないですよね
更にいうと、これらのデータは企業のデータです
我々のような個人事業からスタートする場合は、もっと倒産率は高いと思ってください!
でも誰だって失敗したくないし
好きな事をずっと仕事にしていたいし、起業したら会社員には戻りたくないですよね
その思いは誰もが一緒で、さらにその気持ちの大きさも大差ないと思っています
気持ちの上では大差がないのに、準備に関しては大差がありすぎる
だから結果として倒産してしまうんです・・・
【経営者が現場にいる成長店舗で働く事が一番の開業準備】
正直そう思います
でもそんなお店はほとんどないし、あってもそういうお店には求人が溢れています
なぜなら『経営上手』だからです
そもそも脱サラ組なんかは、年齢だけで就職出来ないから学ぶ事もままならないんですよね・・
じゃぁどうやってサロン経営のノウハウを学べばいいの?
どうやって準備をすればいいの?
どうすれば失敗しないの?
【成功者に聞きまくるしかないでしょう】
【ファニーテールアカデミー 開業セミナー】
![29257510_1701681113223788_1082897762267168768_n[1].jpg](/files/6015/2144/0895/29257510_1701681113223788_1082897762267168768_n1.jpg)
この業界、開業に特化したセミナーはこれ以外ないです
大きな設備投資をしないでも、誰でも開業できるからです
自宅の一室でも開業可能です(用途地域・届出等々必要)
だから準備不足で潰れると言っても過言ではないと思います
このブログを見ているトリマーの方でも将来開業したいという方は沢山いるはずです
開業費用をどこからどのくらい融資を受けるか、決めていますか?
開業予定地をもう決定していますか?
不動産業者は何社とお付き合いしていますか?
土地・賃貸どちらが得意な不動産業者さんか理解していますか?
開業予定地は取扱い業の許可は可能ですか?
開業可能な用途地域か役所に確認していますか?
木工事・内装工事・設備工事は誰に依頼するか決めていますか?
ブログ・SNSは既に影響力をもっていますか?
ドライヤー・ブロアー・マイクロバブル設備投資はどのくらいするか決めていますか?
税務の基礎知識は持っていますか?
・・・等々
分かります?
分からなければ、全て学んで準備をしておかなければ駄目です
以下ファニーテールアカデミーの告知をコピペしておきます
開業を夢見ている方は必ず受けてください
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
講義だけでなく、お店作りをしていく為の実践形式のセミナーです。
【こんな方にオススメ】
【日 程】 単発でもセットで受講してもOK
第1回 5月9日 ①11:00~ 「これから独立を目指す方・迷っている方へ」
第2回 5月9日 ②14:30~ 「あなたという商品づくりを考える」
第3回 6月13日 ①11:00~ 「開業準備(1)お金について」
第4回 6月13日 ②14:30~ 「開業準備(2)開業に必要な知識」
第5回 7月11日 ①11:00~ 「開業準備(3)パワーポイント講座」
第6回 7月11日 ②14:30~ 「開業準備(4)エクセル講座」
第7回 9月12日 ①11:00~ 「店舗計画(1)ハード面 お店のコンセプトから店舗設計を具体的に形にしていく」
第8回 9月12日 ②14:30~ 「店舗計画(2)ソフト面 お店の内面が大事だったりする」
第9回 10月10日 ①11:00~ 「一番難しい“集客力”をつける」
第10回 10月10日 ②14:30~ 「SNS発信 発信しなければないのと同じ」
第11回 11月14日 ①11:00~ 「オープン準備(1)お店の仕組みを作る」
第12回 11月14日 ②14:30~ 「オープン準備(2)小さなお店の経理と財務」
第13回 12月12日 ①11:00~ 「2019年日本のトリミングサロンの流れを考える」
第14回 1月9日 ①11:00~ 「マネジメント 今までの行程を客観的に見直してみよう」
第15回 1月9日 ②14:30~ 「オープン! オープン後の道筋を考える」